「駱駝」(2007年6−7月号) インタビュー
|
||||
雑誌「駱駝」に掲載されたインタビューをレポートしました。この4月、70歳を迎えた加山雄三さん。加山さんの昨今の活動を見る度に、「古希」とは何と若々しいものかと思えてくる。
|
||||
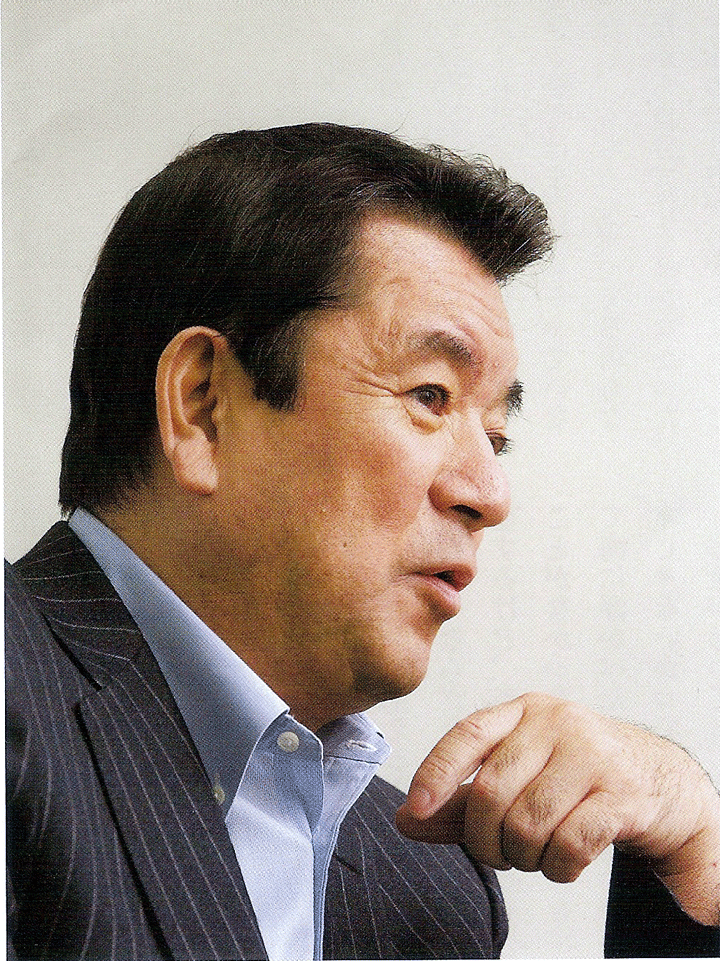 |
||||
07年06月07日新設
|
||||
「駱駝」(2007年6−7月号) インタビュー
|
||||
雑誌「駱駝」に掲載されたインタビューをレポートしました。この4月、70歳を迎えた加山雄三さん。加山さんの昨今の活動を見る度に、「古希」とは何と若々しいものかと思えてくる。
|
||||
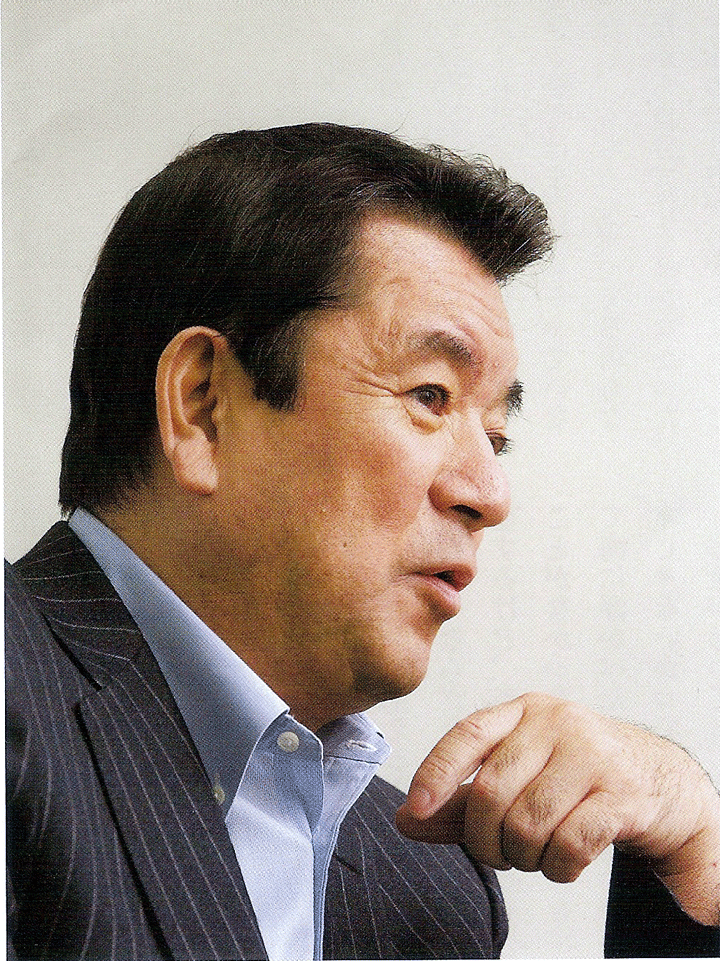 |
||||
07年06月07日新設
|
||||